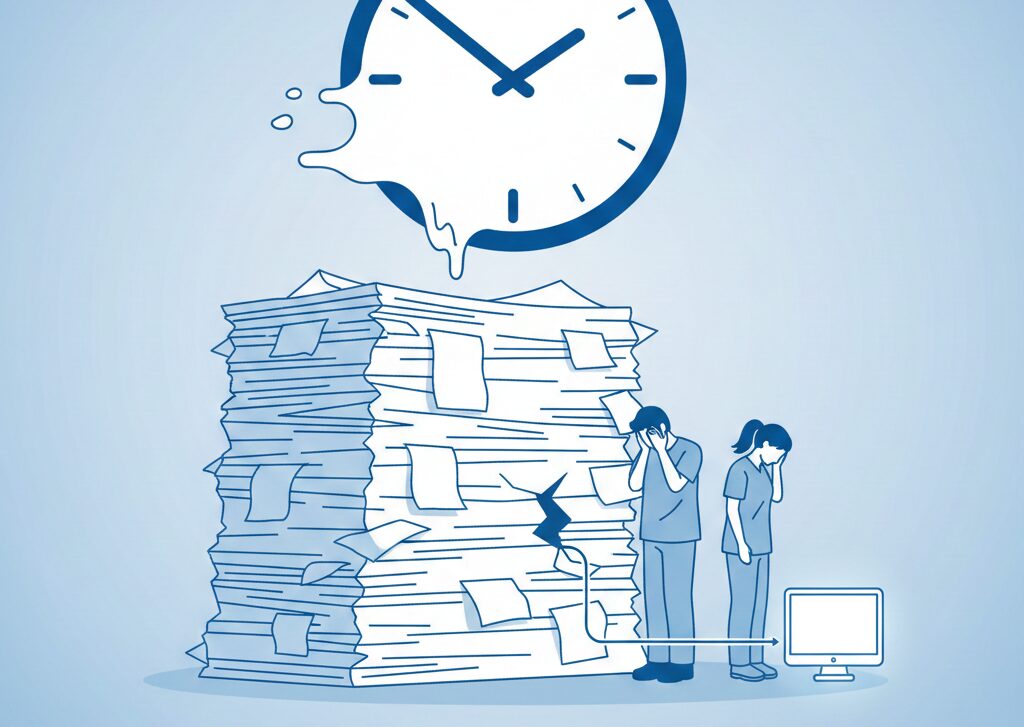革新的なサービスや製品は、日々の挑戦と継続的な改善の積み重ねによって育まれます。特に環境変化が激しく、正確さとスピードの両立が求められるITの分野では、「最新の技術をどう活かすか」が成果を大きく左右します。
私たちが提供するAI₋OCR「AIRead」の開発も例外ではありません。
これまで私たちはどのように意思決定を行い、どのようにサービスを進化させてきたのか。
その裏側には、弊社CEOが大切にしてきた開発マインドがあります。
「自ら動く」という文化が生む推進力
AIReadの開発において、大切にしてきたのは「自ら動く」という文化です。
実際、CEO自ら、当時最新の生成AIモデルであった Claude3.5 Sonnet の検証を行い、これまで夢物語だと思っていたAI-OCRの壁を越える可能性を見出しました。その結果、トップダウンで生成AI-OCRの研究開発の実施とAIReadへの組み込みを決定。検証からプロジェクトの立ち上げまでわずか2週間というスピードで「AIRead on Cloud」の生成AI対応を進めました。
このように、自らが可能性を見つけ即座に試行し検証する。
検証結果と課題を素早く洗い出し次のアクションへ移す、この一連のサイクルを短期間で繰り返すことで、AIReadは日々進化を続けています。
「確証がない挑戦」を可能にする意思決定
新しいテクノロジーを活用した製品開発は、常に不確実性と隣り合わせです。AIReadの開発においても、「これが確実に成功する」という保証はありませんでした。それでも挑戦を続けられたのは、顧客のニーズを深く理解し、それに基づく意思決定を下す文化があったからです。
私たちは、多くの顧客との対話を通じて「同じキーワードが違う場所で3回挙がった時」を、真のニーズが存在するサインと捉えています。複数の異なる顧客から、共通する課題が挙がったとき、次に開発すべき方向性が定まります。
スピードを重視する開発スタイル
さらに、私たちは開発のマイルストーンを「超短期型」で設定しています。顧客からのキーワードで得たヒントを形にする作業に長い時間を掛けず、ごく短いマイルストーンを設定し進めていきます。
大規模で長期的な計画を立てると、途中で環境が変わり、終盤では計画自体が現実と乖離するリスクが高まります。そこで、数日から数週間単位の小さなゴールを定め、それを1つずつクリアしていくことで確実に前進していく考え方を取り入れています。短期間のマイルストーンで「できない」と感じたらピボットする、またはやめるなど、意思決定を素早く行うための小さなゴールを定めるのです。
また、チームビルディングでもスピードを重視しています。新規プロジェクトには社員をアサインすることが理想ですが、既存の業務との兼務となってしまい、どうしても優先度が落ちてしまいます。そこで、まずはオフショア等の外部のリソースを活用し専任チームを立ち上げ、徐々に関連や関心のある社員を巻き込んでいきます。これにより、柔軟かつ迅速なチームビルディングを実現させています。
柔軟な考えと課題解決アプローチ
AIReadは「OCR」という枠を超え、より広い業務課題の解決を視野に入れています。また私たちは実装の手段にこだわらず、顧客の課題解決を最優先に考えています。生成AI-OCRにこだわらず、業務全体の課題解決を目的に、ローコード開発ツール等を活用し素早く機能を実装するなど、様々な技術や手法を組み合わせて解決策を提供しています。
この柔軟な開発姿勢は、「本当に使える」ソリューションの提供につながると考えています。私たちは技術そのものに固執せず、顧客の現実的な課題解決を最優先に考えています。
終わりに
AIReadは、業務に新たな価値をもたらすAI-OCRソリューションとして誕生しました。しかし、私たちの視点は単なる文字認識の精度向上にとどまりません。顧客が本当に望んでいるのは「業務全体の変革(DX)」であり、そこに寄り添い続けることこそが私たちの使命です。
今後も「自ら動く」文化と「スピードを重視する」を信条に、進化を続けるAIRead。
私たちは挑戦を恐れず、さまざまな業界や現場の方々と共に未来を切り拓く存在でありたいと考えています。